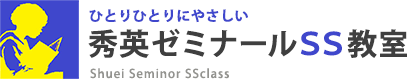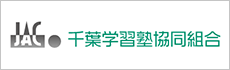最近のエントリー
カテゴリ
秀英ゼミナールSS教室
〒284-0045
千葉県四街道市美しが丘1-16-1
【営業時間】14:00~22:00
【定休日】日曜・祝日(土曜は不定休)
SS教室新着情報&ブログ
HOME > SS教室新着情報&ブログ > 教育のこと > 子どもが自立して学習するようになる勉強法~思考の過程が大切~
SS教室新着情報&ブログ
< 偏差値を10上げる勉強法~国語の勉強法・説明的文章③~ | 一覧へ戻る | 子どもが自立して学習するようになる勉強法~ミスをへらそう~ >
子どもが自立して学習するようになる勉強法~思考の過程が大切~
思考の過程が大事・・・計算はノートに丁寧に書こう
算数や数学が苦手だという子を見ていると多くの場合計算を暗算しようとしています。
数学(算数)のノートを見ても計算のメモ書きや殴り書きの筆算しか残っていません。これでは問題文をどのように読み取って、式をたて、計算をしたのかが判りません。恐らく自分でもよくわかっていないのだと思います。そして、数学(算数)が苦手な子ほど何でもとにかく覚えなくてはいけないと思って丸覚えをしようとする姿が見受けられます。他の科目でも、何でも暗記で切り抜けようとするのはこれが原因だと思います。暗記では、理由や理屈から考えてみる・図に置き換えてみる・イメージを考えるといった解き方の工夫はなかなかできません。
暗算をすると計算ミスをしやすくなります。そしてそのミスに気づくことができません。また暗算をしていなくてもノートの隅にメモ書きなどで済ましていると、文字が汚くて見間違えたり、ズレが起きたり、途中計算を端折ったり…と、なにかとミスが起きやすくなります。基本的には、どんなものでも人間が解くものなのでミスは起きてしまいます。ミスをなくすことよりも、ミスが起きる確率を減らし、ミスが起きてもすぐに気がつけるようにすることが大事なのではないでしょうか。
数学(算数)で大切なのは思考の過程です。どんな手順でどういう計算をしたのかの道筋をしっかり書き残すことが、正しい答えを導くために必要な作業です。これは単純な計算を練習している時でも、方程式を解いている時でも、関数や図形の問題を解いている時でも同じです。式は必ず書く、計算は大きくはっきりと書き、計算過程は残しておく。算数や数学に限らずどの科目でも同様に言えることですが、結局どれだけ細かいことに気をつけられるかが成績アップのカギになってくるのです。ノートは丁寧に書き、思考の過程を書き残す習慣をつけるようにしていきましょう。
秀英ゼミナールSS教室はがんばるきみたちを応援しています。
〜ひとりひとりにやさしい 秀英ゼミナールSS教室〜
カテゴリ:
(秀英ゼミナールSS教室) 2018年11月21日 19:57
< 偏差値を10上げる勉強法~国語の勉強法・説明的文章③~ | 一覧へ戻る | 子どもが自立して学習するようになる勉強法~ミスをへらそう~ >
同じカテゴリの記事
子どもが自立して学習するようになる勉強法~ミスをへらそう~
●ミスをへらそう
「ケアレスミスをしちゃった」というセリフよく聴きますよね。ケアレスミス=たいしたことのないミス(本当はできるのに) というふうに考えていませんか?そして、それは本当にたいしたことのない問題なのでしょうか。
「ケアレスミスをしちゃった」というセリフよく聴きますよね。ケ
よく「次は気をつけてミスをしないようにしよう」と言います。恐らくみんなが思うことです。「ミスしてもいいや」という人はいないでしょう。では「気をつける」って「どこに?」「どういうふうに?」と聞かれたときに答えられますか?「ミスしないように気をつけよう」という言葉は抽象的で具体的に何をするのかがわかっていないので、「気をつけたはずなのにまたミスしちゃった」に繋がるのです。
ケアレスミスは大きく分けて3種類に分類することができます。
ひとつ目は計算の途中、記述の途中で書き間違いをしてしまうことでおきる「単純ミス」
ふたつ目は問題文を丁寧に読んでいない、設問文を最後まで読んでいないことからおきる「読み違いミス」
みっつ目は暗記のしかたが悪いためにすぐに言葉が出てこないことからおきる「暗記ミス」です。
それぞれに対処法があり、解いた問題で起きているミスはどれに属するのか、そして自分はどのタイプのミスをよくしてしまうのか。自分を知ることによりミスを減らすことはできます。
まずは解いた問題について「間違い直しノート」を作りましょう。その時に自分の間違いがミスなのか理解不足なのかそれとも全く手も足も出なかったのかを分類します。分類の時にはさらに詳しくミスはどの種類のミスだったのかまで分析をするとよいでしょう。
「単純ミス」は頭の中だけで考えているためにおきることが多いミスです。対処法としては、「必ず途中式を書く」「記述の文は一度書き出してみる」など自分の書いたものを客観的に見られるように可視化することが必要です。
「読み違いミス」は「記号で答えなさい」と書いてあるのに数字を書いてしまう。「本文から書き抜いて答えなさい」と書いているのに自由に記述してしまうなど、文を最後まで読まないことによるミスなので、文を最後まで読む仕組みを作ることがミスをなくす近道です。たとえば、文の最後の部分に必ず傍線を入れて、「何について聞かれていて、どう答えなくてはいけないか」 をハッキリさせる練習が必要です。
「暗記ミス」は漢字が書けない、英単語のつづりを間違える、重要語句の漢字がでてこない、すぐそこまで出てくるんだけど答えが出てこないなどのミスは暗記の方法を工夫することで改善することができます。暗記というと10回書いて覚えるとか繰り返し読んで覚える、またパッと出てこない言葉は調べて覚えるということをしていると思います。それらは間違いではないですが「暗記ミス」をおこしやすい方法です。暗記したものを答えるという作業は思考力の問題ではなくどういう作業をしてインプットしたかが重要になってくるのです。
「暗記ミス」が少なくなる暗記方法
「暗記ミス」が少なくなる暗記方法